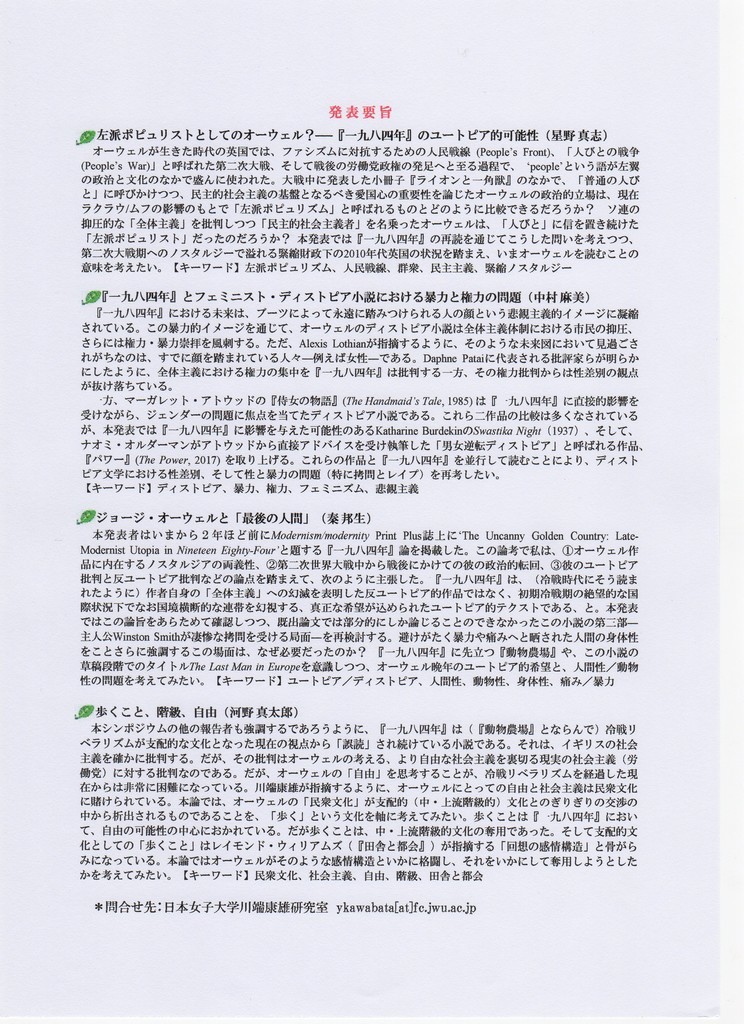「わたしはいまもソーシャリスト」(1896年のウィリアム・モリス)
ウィリアム・モリス(1834-96)は晩年の1890年代は、体調悪化もあって1880年代のような精力的な社会主義活動はおこなえず、ハマスミス社会主義協会を中心に規模を縮小して運動をつづけていた。ケルムスコット・プレスでの本造りに重心を置いたことで、モリスが政治運動から「離脱」した、「変節」したと見る見方が同時代にもあり、アメリカのジャーナリストのルイス・エドウィン・ヴァン・ノーマン(Edwin Van Norman, 1869-1956)はそのような疑問をモリスに問い合わせたようである。モリスは言下にそれを否定する返事をノーマンに返した。1896年1月、モリスが病没する9カ月前のことである。以下、その手紙を訳出する(訳文中の山括弧でくくった語は原語が大文字始まり、太字は原文がアンダーラインの強調。便宜上改行を増やした)。
W. 〔ロンドン西〕ハマスミス、
アッパー・マル
ケルムスコット・プレス
1896年1月9日
拝啓
忙しい身ではありますが、この問題については簡潔にお答えしましょう。〈社会主義(ソーシャリズム)〉についての見解をわたしは変えておりません。芸術と社会主義の関係についての自説は以下のとおりです。
現在の〈社会(ソサエティ)〉(と称されるもの)はまるごと特権階級のために組織されていて、その配置のなかでは労働者階級は機械類としてしか考慮されていません。これは恒久的で膨大な浪費を伴います。そして本当に有用なものを生産するための機構を考えるのは二の次とされているのです。この浪費はこの文明社会をまるごと人為的貧困に陥らせます。ひいてはこれが妨げとなって、すべての階級の人びとが自分の理にかなった欲求を充たせずにいるのです。金持ちは〈俗物根性(フィリスティニズム)〉の奴隷で、貧民は困窮の奴隷というわけです。〔現状では〕わたしたちがみずから欲するものを得るには(部分的にすぎませんが)、莫大な犠牲を払うしか手立てがなく、それができる人などほとんどいません。それゆえ、われわれが芸術にたいしてなんらかの希望をもてるようになるには、まずこの人為的貧困から解き放たれなければなりません。私見では、この点で自由になったときにはじめて、美と出来事にむけての人の自然な本能がしかるべきかたちで発揮され、芸術を欲するようになるのでしょう。そのときには本当の意味でゆたかになるので、われわれはみずからの〔本当に〕欲するものを得られることになることでしょう。
貴殿におかれては、わたしが変節したと考えている向きにこの手紙を見せていただいて構いません。なんでしたら活字にして公表していただいても結構です。
この問題に係る何冊かの拙著とパンフレットの表題を付しておきます。
敬具
若干の注記:初出は『アメリカン・フェビアン(American Fabian)』第2巻2号(1896年4月)。この書簡の現物はブリティッシュ・ライブラリー所蔵(BL, Add. MSS. 52738; Kelvinの書簡集2442番)。署名もふくめてすべて秘書のシドニー・コッカレル(Sydney Cockerell, 1867-1962)の筆跡。多忙でありかつ体調もすぐれなかったモリスのためにコッカレルが口述筆記した。
小野二郎「ラスキンとウェスカー」
「小野二郎著作集」に未収録のエッセイ「ラスキンとウェスカー」(1982年)を以下に掲載します。
ラスキンとウェスカー
小野 二郎
一九七三年の秋のことだったと思うから、もう九年近くの前のことになる。当時ロンドン郊外に滞在していた私のところにウェスカーから思いがけずに手紙が舞いこんだ。
あなたがウィリアム・モリスの仕事を調べに今ロンドンに来ていることをO氏の便りで知った。ついては優秀なモリス研究者を紹介するから、遊びに来ないかという文面である。その五年ほど前、〈ウェスカー68〉という宮本研、木村光一、小田島雄志、津野海太郎などの人びとがグループをつくり、彼を日本に招いて講演、シンボジウ厶をおこない、「三部作」を上演したことがあった。私などはその周辺をうろうろしていたに過ぎないが、彼の作品の翻訳刊行にわずかばかり関係したことがあって、私の名を記憶していたのであろう。
約束の日のお昼に私たち夫婦は、ロースト・ビーフと自家製のヨークシャ・プディングと林檎酒の饗応に与った。バーミンガム大学に提出する論文を準備中という中年女性の研究者は快活で親しみ深いお人柄のように見受けたが、この人を交えて当然話題はモリスのことになった。するとほとんど唐突に私に向って「あなたはモリスを勉強している以上、余儀なくラスキンを読まされただろう、ラスキンのことをモリスと較べてどう思うか」と質問してきた。私が「う?」という顔をしていると、「つまり、思想家としてはラスキンのほうが独創的だと私は思うが、あなたはどうか」と重ねての質問である。私が「う、う」とつまっていると、かの女史が、「思想家としてはラスキンが偉いかもしれないが、実践家としてはモリスが偉い。」といった。ウェスカーは言下に「そんなことをいったって、モリスの実践は失敗だったじゃないか。」と勢いこむ。
マルクスとレーニンのどちらか偉いかといわれたって困る。評価軸が違うだろう。それにモリスの実践といったって、社会主義者としては失敗したかもしれないが、デコラティヴ・アーティストとしては大成功したし、詩人としても成功したじゃないか、などとやくたいもないことをぐずぐず頭のなかで考えたような記憶はあるが、このギロンがどう落ち着いたか忘れてしまった。
しかし、今思って見れば、いやその後時々思い返しているのだが、ウェスカーが委細かまわず、モリスの実践の失敗をいい切ったのは、むしろ社会主義者としての失敗は芸術家としての失敗に他ならぬという思いを伝えたかったのではなかろうか。さらにいえば、かれは、自らの〈センター42〉の失敗を若気の過ちとして見ておらず、芸術家としての失敗と自覚しているということだろう。
〈センター42〉。六〇年代の始め、労働運動に文化運動をぶつけようという目的のための組織的な試みであった。組合運動のなかで文化活動を盛んにさせるということではない。そうではなくて、労働の自立のための希望の原理は芸術への関心のなかにあるということ、労働の解放の手だてもまた芸術への興昧のなかにあるということ、そういう事実そのものに労働者階級に目覚ませようというのである。
生きるということの喜び、これを与えることが芸術のもっとも基本的な役割りであろうが、にせの喜びで誤魔化されないよう、絶えず本物の喜びを教えてくれるのも芸術の役割りである。文字通りの飢えからの解放だけが、運動の動機でない以上、人間としての欲望の溌溂たる充足に労働運動が根拠を置かなければ、その運動は人間解放の運動にならないではないか。
しかし「溌溂たる充足」は欲望の質と関係する。この問題に溌溂と目覚めさせること自体芸術の役割りである。
これはまた、ウェスカーの劇作の当初のモチーフそのものであった。それがそのまま〈センター42〉の運動のモチーフになっていたのである。しかし、労働組合は欲望を古い殻に閉じ込めて、この呼び声に耳を藉さなかった。ウェスカーは失敗した。
以後、失敗がかれの劇作のテーマになる。少くとも主要なテーマの一つになる。『彼ら自身の黄金の都市』『友よ』そして、この『青い紙のラブレター』。失敗の情況は次第に削られて行き、失敗そのものが主題になってしまう。『青い紙のラブレター』の老いたるかつての組合指導者が引用するラスキンは、ウェスカーやあるいはモリスを導いた、あの熱っぽい思想の鼓吹者ではなく、晩年の錯乱の色濃く、死の影のにじんだ、自伝的作品『プラエテリタ』からである。
ラスキンは実践において失敗しなかったか。失敗した。「聖ジョージ・ギルド」の試みである。この試みは、その中身を紹介する気になれぬほどつまらなく、試みといえるようなものでないかも知れぬ。それは、あの巨大で複雑な陰影に富む思想を、実践的計画綱領に凝縮し、要約したというようなものではない。すこぶる不得要領で、理想的で実行不可能な内容というより、間違った行動原理をふくんでいるとさえいえるだろう。もし、これをラスキンのユートピアと呼べるなら、「このユートピアは史上数あるものの中で最も不鮮明な、最も退屈なものの一つであろう。」という批評は当っていると思う。
つまり、これは失敗とさえいえないものだ。運動は、その内包する思想を、挫折や失敗の形でしか伝えられない場合がしばしばある。モリスの場合がそうだ。ラスキンの思想の独創性とは何か。人を失敗させる力だといいたい。
モリスにとってのラスキンとは、モリスが青年時代に読んだ若き日のラスキンである。それを理論ともし、情熱ともして、長い間、ものを作り、形を生み出した。そういう実践を通じてその思想の孕むヴィジョンが次第にくっきりと姿を現わすようになり、そして新しい行動を促し、その失敗によってしか、表現できない何かを表現した。
そこへゆくと、ウェスカーは未だ十分に失敗してはいないだろう。かれがラスキンの思想の独創性をいった時、直接に実行を導き出すことの難かしい、一個鬱然闇闇たる思想の団塊を想っていたのかも知れない。それをわざわざ、かれウェスカーがいい立てるようにしたのは、己れの〈センター42〉の失敗を「聖ジョージ・ギルド」の失敗にもならぬ失敗と重ね合わせ、無視し、もっと大きい失敗を夢想したのかとも思う。
いや、そうではなかろう。ラスキンの思想を実行に移すなら、モリスのように、大らかにそのメッセージの中核と信ずるところを、大胆に、あるいは素朴に受取り、それをマルクスにぶつける方向がやはり、伸長力のある世界を展開できるのであろうが、その豊かなモリスの失敗を豊かに昧うとすれば、そして〈センター42〉の失敗を昧いつくそうとすれば、エロティックなまでに向日的なモリスよりも、異常な視力と臭気さえ発する自省の苦汁とがもつれ合い、くねり、そして飛翔するラスキンの思考の跡を尋ねることになったのではなかろうか。思考の進め方の中に、失敗の自覚的先取りがあるからである。
実行上の失敗によってしか見えないものを文体のなかで発見しようとする。モリスが行き着いたところから出発したともいえるウェスカーは逆の路を辿ったといえるか。〈センター42〉の失敗がなければ、ラスキンをこうは読めないという読み方。こうしてラスキンの文体のなかに発見したもの、というより発見したかたちを、芝居の上で再現しようとしている……。
しかし、舞台で強調されるはずの、オレンジを切る手さばきの、熟練した迅速さが、かえってゆったりした時間の流れを伝えるのはモリスのデザインの昧に近いのである。(1982年)
*(後記)ここに採録した小野二郎(1929-82)の「ラスキンとウェスカー」は、劇団五月舎によるアーノルド・ウェスカー作『青い紙のラブレター』の公演パンフレット(1982年4月)に掲載されたエッセイである。執筆はおそらく1982年3月下旬、著者が急逝する一月前のことだった。
これは晶文社版の『小野二郎著作集』(全3巻、1986年)に収められていない。著作集を編んだ際に編者たちの目をすり抜けてしまったためである。ちなみに編者名は記されていないが、著作集の立案は津野海太郎氏が中心となり、島崎勉氏(晶文社編集部、当時)、それに川端が加わって三人で構成を練った。1985年の夏の一日、晶文社近くの旅館の一室で三人で長時間編集会議をしたことを覚えている。「ウィリアム・モリス研究」「書物の宇宙」「ユートピアの構想」という各巻のタイトルもその日にもう決めたのではなかったか。
ラスキンとウェスカー(またモリス)の思想をめぐり、彼らの「挫折」や「失敗」に積極的な意義を見出しつつ評価する文章は小野ならではのものであり、ラスキン論としても独特な知見が示されていると思われる。これを見落として著作集に入れ損ねたのはわれながら惜しかった。上記の公演パンフレットをわたしがたまたま古書ネットで発見し入手したのは2008年春のこと。『ラスキン文庫たより』第57号(2009年10月)に再録したが、さほど多くの読者の目にふれたとは言いがたい。それで今回、小野二郎の回顧展(「ある編集者のユートピア」展、世田谷美術館、4/27~6/23)がまもなく開かれる折でもあるし、ここに新たに再録することとした。掲載を許可してくださった小野俊太郎氏(小野二郎のご長男)に感謝申し上げる。(2019年3月15日、川端康雄記)
講演会のお知らせ
日時:2019年3月16日(土)14時~
場所:早稲田大学 文学学術院(戸山キャンパス)33号館16階 第10会議室
講師:川端康雄(日本女子大学)
司会:庄子ひとみ(順天堂大学)
※一般の方もご自由に参加できます。参加費無料、予約不要。
(発表要旨)
小野二郎(1929-82年)は1955年に東京大学教養学部教養学科イギリス分科を卒業後、同大学院人文科学研究科比較文学比較文化修士課程に進学、島田謹二を指導教授として1958年3月に修士課程修了、同年4月に弘文堂に入社し出版編集者となった。1960年に中村勝哉と晶文社を設立、同年に東海大学の専任教員となって出版社員と大学教員を兼務することとなり、1963年に教員としての所属が明治大学に代わって以後もそれが終生つづく。
小野のライフワークはウィリアム・モリス研究であった。モリスを単独で扱った論考は中公新書版の『ウィリアム・モリス――ラディカル・デザインの思想』(1973年)を嚆矢とするが、晶文社から出した初期の評論集『ユートピアの論理』(1969年)と『運動としてのユートピア』(1973年)も頻繁にモリスに言及しているのみならず、同時代の政治・社会・文化の批評のため常時モリスを参照枠としていたことは、後者のあとがきで「これら〔の評論〕はいわばすべてウィリアム・モリス勉強の副産物であるが、むしろモリスを問題にする意味を絶えず問い直すための作業ともいえるかもしれぬ。今日のわれわれの問題のひとつひとつをモリスだったらどう考えるかを考えるというのが、自然な私の習慣になっていたからである」という一文からもうかがえる。
1973年初夏から1年間在外研究でロンドンを拠点としてモリスとその追随者たちの装飾芸術作品についての本格的な実地調査をおこない、帰国後にその成果を発表、それが『装飾芸術――ウィリアム・モリスとその周辺』(青土社、1979年)に結実する。さらに、装飾芸術史こそ民衆の歴史とみなすモリスの立脚点をさらにイギリス民衆の生活史の枠に押し広げて、食文化からヴィクトリア朝の絵本、ミュージックホールまでさまざまな文化事象を論じた成果が『紅茶を受皿で――イギリス民衆文化覚書』(晶文社、1981年)で、これはその後に興隆するイギリス生活社会史の先駆的な仕事であった。さらにケルムスコット・プレスを中心としたタイポグラフィ論(「書物の宇宙」)を連載し、モリス研究をさらに展開していこうとした矢先に、1982年に52歳の若さで急逝した。
小野の没後、この30有余年にモリス研究はデザイン、文学、社会主義運動、環境保護運動など、さまざまな分野で大いに進捗した。それらをふまえていま見直すと、小野のモリス論のなかには細部において修正すべき点もあることは否めない。とはいえ、現在と比べてモリスへの一般的な関心があまりなかった時代にこの思想家に注目し、装飾芸術史と社会主義運動史の両面からその仕事を総合的に捉えようとした試みは貴重であり、本質的に小野の論考はいまもまったく価値が薄れていない。2019年春には彼の仕事の今日的意義を探る回顧展「ある編集者のユートピア」も予定されている。
小野が駆使した装飾デザインの分析法は、学生時代に比較文学のゼミで島田謹二から仕込まれたexplication de texteの独特な変奏であったように思われる。そのような手法を駆使してのモリス・デザインの分析をとおして「社会主義の感覚的基礎」をラディカルに語った「自然への冠――ウィリアム・モリスにとっての「装飾芸術」」(1975年)等の一連の論文は小野のモリス研究の最高の到達点を示す。
ウィリアムズ『辺境』の訳者解説
レイモンド・ウィリアムズ『辺境』(小野寺健訳、講談社、1972年)。書架から取り出して訳者解説を謹んで再読。味わい深い、平易な文章で、ウィリアムズの小説の急所が的確に語られている。
そのなかに小野寺先生ご自身の少年時代の非常に印象的な回想が挟み込まれている。以下、引用する。
戦争の末期に中学生だった私は、農村動員で横浜近郊の農家に泊まりこんで、農作業を手伝ったことがある。
その一軒の農家の老人が、畑仕事の休みに煙管(きせる)で煙草を喫(す)う姿を見るたびに味わった恍惚感を、私はいまでも忘れられない。その人は実においしそうに煙草を喫った。煙草に浸りきって何も見えないような風情だった。以来、私はこんな風に煙草を喫う人に、こんな休息のとり方をする人に出会ったことがない。傍に腰をおろしていた少年の私までその雰囲気に陶然と酔って、いつまでも喫っていてくれるようにと祈ったくらいだった。どうすれば何かをそんな風に楽しめるのか教えてください、と言いたいくらいだった。それが農民の生活のリズムに根ざしているのだということなどは、当時の私には思いつけるはずもなかった。彼の鍬の使い方も、その息子さんだった三十がらみの人のそれとは違って、思えばこの煙草の喫い方と一致していたのである。
訳者がこの老人の立ちふるまいを強く心に留めているのは、言われているように、その後の人生で見かけなくなった姿であるからだ。その姿は、『辺境』の小説世界でいえば、主人公マシュー・プライスの父親であるジャック・プライスの居住まい・佇まいと重なる。たしかにこの小説でも「こういう感覚はジャック・プライスで終っている。そして人間は、この時、たしかに何か大きな体験をその文化の中から失ったのに違いない。」
近代の英国小説においてはこうした文化の残滓をハーディやロレンスの作品世界に見ることができる。「田園を破壊する憎むべき敵」としての産業化の批判と抵抗――その「伝統」をウィリアムズもまたロレンス経由で継承しているといってまちがいないだろう。
だがそこを見るだけでは、つまり、ある体験の喪失を強調するだけでは、ウィリアムズの小説の勘所を捉えそこねてしまう。そこをしっかりと読み取ったうえで、小野寺先生はつぎのように指摘しておられる。
しかし、ウィリアムズは産業化を告発して田園を愛惜するところで立ち止まってはいない。『辺境』のさいごのシーン、ロンドンのパディントン駅に帰りついたウィルが、あわただしく地下鉄に向って歩いて行く群衆の中を急いで行くところは、ウィルがもはや現実となった「近代社会」と何とか対決しようとしている決意を思わせる。その決意は今のところ暗く悲壮である。しかし辺境のグリンモーからかつて都会へ出て来た彼は、こんどはその都会の生活そのものが新たな辺境であることを自覚し、その辺境文化の中から価値あるものを建設するほかに道はないと思っているように見える。(小野寺健「『辺境』解説」)
スポーツ精神
ロシア・サッカーの名門ディナモ・モスクワが英国に遠征したのは第二次世界大戦の終結後まもない1945年秋のことだった。UEFA(欧州サッカー連盟)設立の9年前で、英国では海外のクラブとの対戦は親善試合でさえも珍しく、開催された4試合とも満員の大観衆を集めた。対戦相手と結果は(試合順でいうと)チェルシーと3-3のドロー、カーディフ・シティに10-1の大勝、アーセナルに4-3で勝利、グラスゴー・レンジャーズと2-2のドローだった。対戦前の予想ではサッカーの「母国」の名門クラブと共産国の「アマチュア」クラブとでは比較にならないだろうといった、強気というか楽観的な記事が散見されたが、ソ連リーグでこの年優勝を遂げたディナモは、華麗なパスサッカーと流動的なポジションチェンジの戦術を駆使し、一敗もすることなくモスクワに凱旋帰国した。英国サッカー界は面目をつぶした。
それからまもなく、作家のジョージ・オーウェルが「スポーツ精神」(The Sporting Spirit)というエッセイを『トリビューン』紙に寄稿した(1945年12月14日号)。冒頭にこうある。
ディナモ・フットボールチームの短い訪問が終わったので、ディナモがやってくる前に多くの思慮深い人びとが内輪で話していたことを公表してもよかろう。すなわち、スポーツというのは必ず敵意のもとになるということ、今回のような訪問が英ソ関係に何らかの影響をおよぼすとしたら、以前よりもいささか悪化させることにしかならない、ということだ。
オーウェル自身は観戦しなかったようだが、右の見解を裏付けるのに、アーセナル戦では乱闘があって審判がブーイングを受けたこと、グラスゴーでは最初からつかみ合いの乱闘だったという伝聞を記す。じっさい、前者の試合は濃霧で視界がきかず中止にしたほうがよい状況だったのをソ連の審判(ディナモ側の要求でこのゲームはソ連の主審が笛を吹いた)の判断で決行、ラフプレーでアーセナルの選手が退場処分を受けたのだが、霧に紛れて退場せずしばらくプレイしつづけたとか、およそ20分間ディナモ側がピッチ上に12人いたとか(途中交代の行き違いだったと説明されるが)、はたまたソ連の主審が英国人副審二人を片側のサイドに配置して別サイドを自分で兼任した(そうすることでオフサイドを黙認してディナモの勝利を演出した)とか、冗談のような挿話が残っている。
オーウェルはつづけて「いかにもこのナショナリズムの時代らしく、アーセナルがロシア人の主張するようにイングランド代表チームだったのか、あるいは英国人の主張するようにクラブチームにすぎなかったのか……例によってだれもが自分の政治的先入観に従って答えを出している」という。これも補注を入れるなら、この時期は従軍した選手がまだ全員復員しておらず、チェルシーもアーセナルも戦力不足を補うために急遽他のクラブから何人か助っ人を確保して対戦した。アーセナルはブラックプールからスタン・モーテンセン、ストーク・シティからスタンリー・マシューズを呼んだ。それでこれはクラブチームでなくてイングランド代表ではないかという見方が出たわけだが、じつはディナモのほうもこの年ソ連リーグの得点王となったフセヴォロド・ボブロフをCDKAモスクワ(現CSKAモスクワ)から借り受けて出場させていたので、混成チームであるのは同様だった。
ともかくディナモの遠征は、何らかの結果をもたらしたとするなら、双方に「新たな憎悪」を生み出したというのがオーウェルの見解だ。
それも当然のことだ。スポーツは諸国民のあいだに友好の念を生むとか、各国の庶民がサッカーやクリケットをやれば戦場で相まみえる気がなくなるだろう、などと人が言うのを聞くと、わたしはいつも呆れかえってしまう。……国際的なレヴェルではスポーツはまぎれもなく疑似戦争なのである。
「スポーツ精神」というタイトルからしてそうだが、これはいかにもオーウェルらしい挑発的なエッセイで、思惑どおりというべきか、直後に読者から怒りを含む反論の投書が寄せられ、しばし同紙で論争がつづいた。
わたし自身、40年来サッカーに格別の愛着をいだいてきた者として、「スポーツ精神」のこのひたすら否定的な定義に若干の戸惑いを覚えるのはたしかだ。それでも、近代スポーツとナショナリズムとの密接な関係を考えてみるなら、国威高揚、ショーヴィニズムの鼓舞、あるいは支配者による国民の馴致などのためにスポーツが利用されてきた事例は枚挙にいとまがないわけであり、そうした歴史を顧みずに「スポーツ精神」を無条件に理想化するのは無邪気にすぎる。その点でオーウェルの近代スポーツ観は一種の解毒剤として有用であると思う。
スポーツを語る言葉に戦争の比喩が多用されることは「疑似戦争」としてのスポーツという位置づけを裏書きする。「アジアの大砲」だとか「アジアの核弾頭」といった表現がサッカージャーナリズムで頻出するようになったのはいつごろだったか。今回の〔2014年ブラジル〕ワールドカップの準々決勝、ブラジル対コロンビア戦の前日にネイマールはインタビューに答えて、「また戦争のような試合になる。それでも勝つのはブラジルだ」と言い切った(『日刊スポーツ』2014年7月4日付)。たしかに戦争のようになって、今大会最大の華は散った*1。
その数日前、決勝トーナメントのたけなわに、日本では戦争に一歩踏み出す方向に舵が切られた*2。「スポーツ精神」が発揮されて、と言うべきだろうか。
(en-taxi vol.42 Summer 2014より転載。一部語句修正)
*以下はディナモ・モスクワの英国遠征と対アーセナル戦を伝える当時のニュース映画
www.youtube.com